クラウドファンディングで支援金を集めたら「全部自分の収入になる」と思っていませんか?
実は、購入型クラウドファンディング(リターンあり)の場合、税金がかかるケースがあります。
税金を知らないままプロジェクトを進めてしまうと、後から大きな負担が発生することも。
本記事では、初心者でも分かるように「購入型クラウドファンディングと税金の関係」を徹底解説します。
購入型クラウドファンディングとは?
購入型クラウドファンディングとは、支援者がお金を支援し、その見返りに「商品やサービス(リターン)」を受け取る仕組みです。
例としては、以下のようなケースがあります。
- 新しいガジェットを開発 → 支援者に完成品を届ける
- 飲食店が新メニューを開発 → 食事券を支援者に配布する
- アーティストがアルバム制作 → 完成したCDやグッズを提供する
つまり、支援金は「寄付」ではなく「商品やサービスの販売代金」に近い性質を持っています。
ここが、税金が発生する大きなポイントです。
購入型クラウドファンディングにかかる税金の種類
購入型クラウドファンディングで集めた支援金は、原則として「売上」として扱われます。
そのため、以下のような税金が関係してきます。
- 所得税(または法人税):個人事業主や法人の収入として課税
- 消費税:課税事業者の場合、リターンの提供に消費税が発生
- 住民税:所得に応じて課税
特に重要なのは「支援金=収入」となるため、確定申告で申告が必要になる点です。
課税の具体例
数字を用いて、どのように税金が発生するのか見てみましょう。
例1:個人で30万円を集めた場合
- 集めた金額:300,000円
- 製品制作費:150,000円
- 利益:150,000円
この場合、利益部分が課税対象になります。会社員の副業として行った場合は「雑所得」として申告が必要です。
副業所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。
例2:法人が100万円を集めた場合
- 集めた金額:1,000,000円
- 製品制作費:600,000円
- 利益:400,000円
この400,000円は「売上」として法人税の課税対象となります。
また、リターンに消費税がかかる場合、消費税の納税義務も発生します。
よくある誤解:支援金=寄付ではない
初心者が最も勘違いしやすいのが「クラウドファンディングだから寄付扱いになる」という思い込みです。
購入型の場合は、支援者は「お金を払って商品やサービスを買っている」ため、寄付金控除の対象にはなりません。これは大きな注意点です。
税金対策としてできること
クラウドファンディングで成功した後に「思ったより税金が高くて赤字になった」というケースを防ぐために、次のような準備が有効です。
- 事前に収支計画を立てて「税引き後の利益」をシミュレーションする
- プロジェクトページでリターン価格を設定する際に、税金分も考慮する
- 経費(材料費・配送費・手数料など)をしっかり記録しておく
- 専門家(税理士)に相談する
初心者が知っておくべきポイントまとめ
購入型クラウドファンディングにおける税金の基本をまとめると、以下の通りです。
- 集めた支援金は「収入」として扱われる
- 利益に対して所得税・法人税がかかる
- 消費税の対象になる場合もある
- 寄付扱いにはならない
- 確定申告が必要になるケースが多い
まとめ:購入型クラウドファンディングでは税金対策が必須
クラウドファンディングは夢を実現できる素晴らしい仕組みですが、税金の知識がないと「成功したのに赤字」という残念な結果になってしまうこともあります。
支援金は収入であることを理解し、あらかじめ税金対策を行いましょう。
もし「自分の場合どうなるのか分からない」という方は、プロジェクト開始前に税理士に相談することを強くおすすめします。

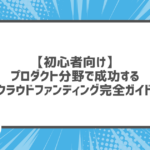
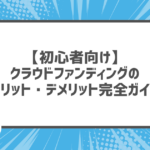
コメント